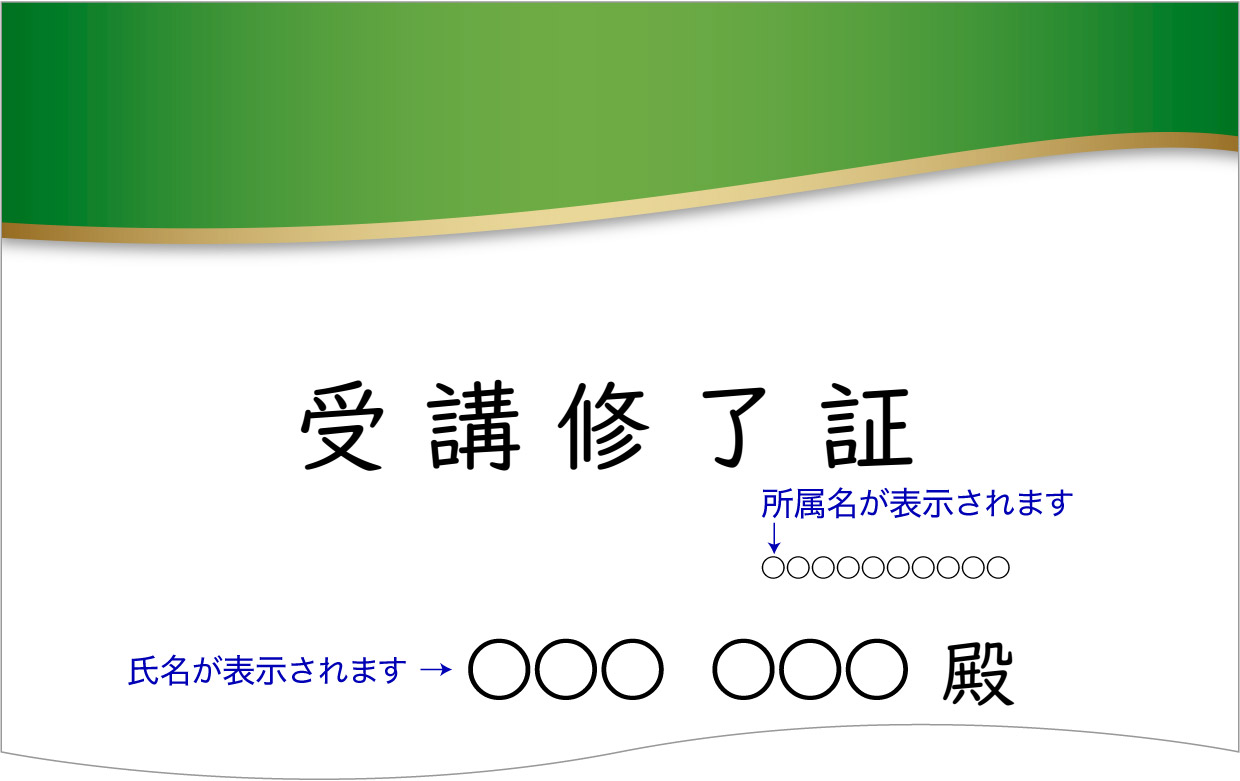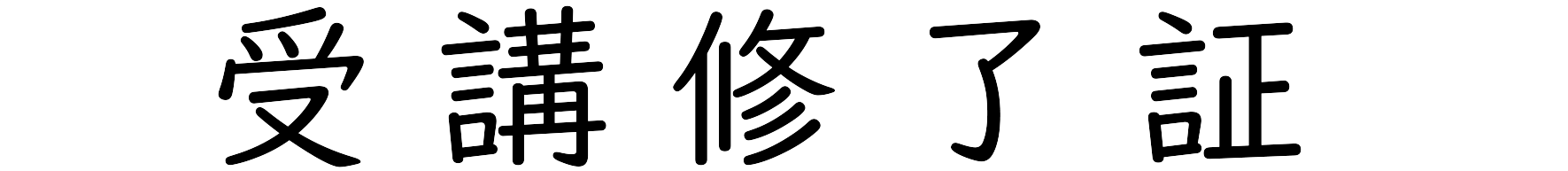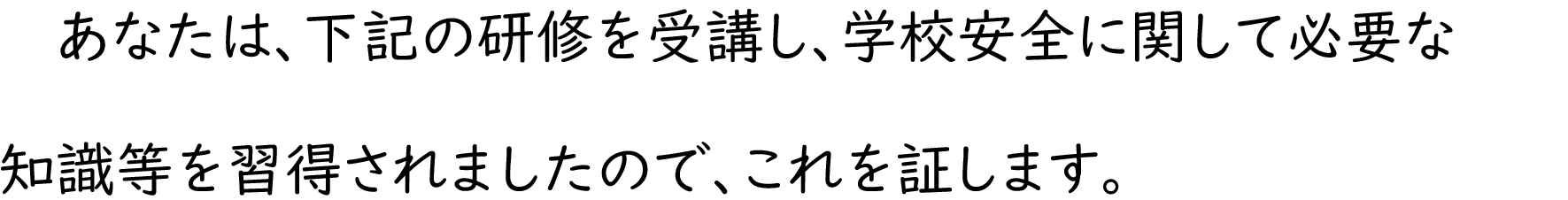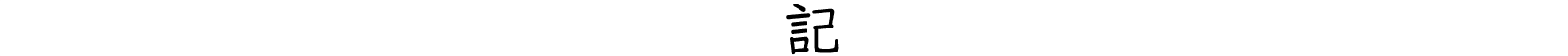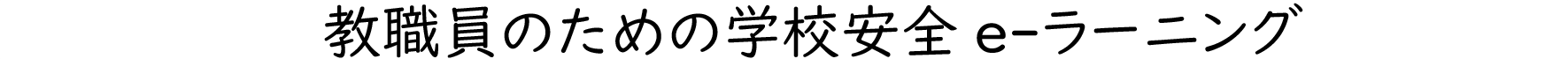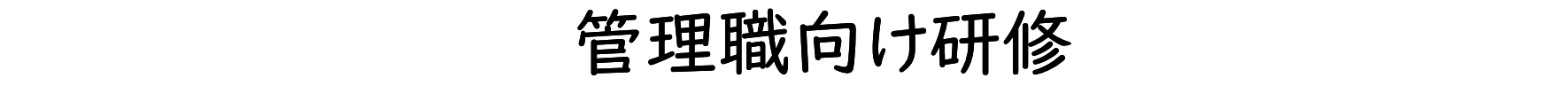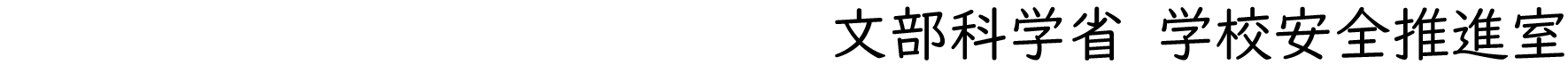管理職向け研修
本研修の対象者
- 管理職、又はそれに準ずる立場にある教職員
学習目標
- リーダーシップを発揮して、校内における学校安全の活動を推進することができる。
- 学校安全の活動推進に当たり、家庭・地域、関係機関等との連携・協働を推進することができる。
- 事件・事故・災害等の発生時に、的確な状況判断・意思決定を行うことができる。
※動画標準再生時間:約16分
求められる資質・能力
-
学校安全の推進に必要な組織活動に関し、以下の事項を理解している。
- 校内の協力体制構築の重要性、協力体制構築に当たっての留意点(目標・方針の共有、異論を含めた意見聴取・議論、平時からの安全意識維持・高揚)
- 教職員研修の重要性、校内研修・伝達の方法、新たな研修・訓練方法の概要
- 家庭・地域・関係機関との連携体制の構築方法
-
組織のリーダーとして、安全管理のうち特に災害発生時以降の対応について、以下の事項を理解し、リーダーシップを発揮して対応することができる。
- 状況に応じた意志決定の必要性・重要性
- 引き渡し判断の重要性
- 教育活動の継続に向けた応急教育計画策定の必要性
- 避難所対応における学校の役割及び事前協議の必要性
- 調査・検証・分析・再発防止のうち、初動対応時に学校で実施すべき事項及びその留意点
- 児童生徒等の心のケアの必要性
問1
次のア~エの中から、次の文中の空欄a~cに入る言葉の組合せとして
適切なものを1つ
選びなさい。
学校安全の活動を効果的に進めていくためには、[ a ]・安全管理の活動を学校運営組織の中に具体的に位置付けることが重要であるため、管理職のリーダーシップの下、[ b ]や危機管理マニュアル等に基づいた組織的な取組を的確に行えるよう協力体制を構築するとともに、全ての教職員がキャリアステージに応じて必要な[ c ]に関する資質・能力を身に付けることが必要である。
正誤判定

学校安全の活動を効果的に進めていくためには、 安全教育 ・安全管理の活動を学校運営組織の中に具体的に位置付けることが重要であるため、管理職のリーダーシップの下、 学校安全計画 や危機管理マニュアル等に基づいた組織的な取組を的確に行えるよう協力体制を構築するとともに、全ての教職員がキャリアステージに応じて必要な 学校安全 に関する資質・能力を身に付けることが必要です。
問2
次の中から、校内の協力体制構築に関する記述として最も 適切なものを1つ 選びなさい。
正誤判定

校内の協力体制を構築するためには、学校安全の中核となる教職員を 校務分掌に位置付け 、その教職員を中心に、 全ての教職員が一体となって 学校安全を推進する体制を整備します。教職員の危機管理意識の維持・高揚は、 訓練・研修などの機会はもとより、職員会議などさまざまな場や機会を活用 して行います。また、危機管理マニュアルの作成・改善は、 家庭・地域・関係機関と連携 しつつ実施します。
問3
次のア~オの中から、次の文中の空欄a~cに入る言葉の組合せとして最も
適切なものを1つ
選びなさい。
[ a ]事件・事故・災害の対応を考える上では、校内組織での検討や話し合いの場で、様々な観点から[ b ]議論をしておくことが必要であり、組織のリーダーである管理職等は、若手教職員の発言を促したり、出された意見をすぐに否定したりしないなど、異論や反論を言い出しやすい[ c ]を作ることが望まれる。
正誤判定

多種多様な 事件・事故・災害への対応を考える上では、校内組織での検討や話し合いの場で、様々な観点から 幅広い 議論をしておくことが必要であり、組織のリーダーである管理職等は、異論や反論を言い出しやすい 雰囲気 を作ることが望まれます。
問4
次の中から、教職員研修の実施に関する記述として最も 適切なものを1つ 選びなさい。
正誤判定

学校安全の中核となる教職員は、国が実施する「学校安全指導者養成研修」や、各地域で実施されている学校安全研修などの 校外研修に参加 して、 様々な情報を学内に持ち帰り 、校内研修の推進役としてこうした情報を 活用する ことが望まれます。
問5
次の中から、家庭・地域・関係機関等との連携に関する記述として最も 適切なものを1つ 選びなさい。
正誤判定

学校安全推進のための連携体制を構築する上では、 校種や設立主体の異なる学校とも既存の委員会組織などを活用するなどして連携 します。連携の場では、学校安全計画や危機管理マニュアルの作成・見直しについて 意見・助言を受けたり 、作成した計画・マニュアルを周知して 協力を要請 します。保護者や地域に対しては、 学校と家庭や地域が共に学校安全に取り組む という考え方を浸透させます。関連の ボランティア団体の協力を得ることも有効 です。
問6
次の中から、危機発生時の緊急対応・発生後の対応についての記述として最も 適切なものを1つ 選びなさい。
正誤判定

事前に定めたマニュアルの想定を超えた事象が発生する場合には、
管理職がリーダー
として、「児童生徒等の生命と健康が最優先」という
基本原則に立ち返って、最善と思われる判断を下す
ことが必要です。児童生徒等の引渡しと待機の判断も、
管理職
が行います。
学校が避難所となった場合でも、教職員の第一義的役割は
児童生徒等の安全確保・安否確認、教育活動の早期正常化
です。
問7
次の中から、学校事故等の発生後の学校の対応として 適切でないものを1つ 選びなさい。
正誤判定

事故等の発生後に実施すべき対応としては、「安否確認」、「引渡しと待機」、「 教育活動の継続 」、「避難所としての対応」があります。教育活動の継続については、 学校が 、学校機能の早期回復を図るため、設置者等と協議・連携して、地域や学校の実態に即した応急教育の計画を策定します。
問8
次の中から、学校事故発生後の応急教育計画を立案する上での留意点として 適切でないものを1つ 選びなさい。
正誤判定

事故発生後の応急教育計画を立案する上では、 給食提供の再開 についても留意しておくことが必要です。
問9
次の中から、「学校事故対応に関する指針」に示されている初期対応時(事故後一週間程度)の対応として 適切でないものを1つ 選びなさい。
正誤判定

「学校事故対応に関する指針」では、初動対応期(事故後一週間程度)に行った 基本調査の結果、必要と判断される場合 に、専門家等による詳細調査を行うこととされています。
問10
次の中から、学校事故の基本調査に関する記述として 適切なものを1つ 選びなさい。
正誤判定

死亡事故をはじめ重大な事故等が発生した場合には、 学校が主体 となって「基本調査」を実施します。原則として3日以内に、 関係教職員や現場に居合わせた児童生徒等への聴き取り を実施します。 基本調査の結果、必要と判断される場合 には、学校設置者が主体となって、専門家等からなる調査委員会による「詳細調査」が行われます。
結果
「再テスト」ボタンをクリックすると再度テストに解答できます。学習しなおす場合は、目次から学習したいページをクリックしてください。
当コースの学習はこれで修了です。以下の手順で修了証を発行してください。
【ご注意】
- これから修了証発行まで画面を進める際は、絶対にブラウザの[戻る(←)]ボタンは使わないでください。当ボタンをクリックすると当教材のTOPページが表示され、最初からテストをやりなおすことが必要になります。
- 入力確認画面で[修了証を発行する]ボタンをクリックすると、再入力できませんのでご注意ください。
【修了証発行手順】
- 下端の所属欄、氏名欄に入力し、[入力内容を確認する]ボタンをクリックしてください。所属欄は2行まで改行可能で、2行あわせて30文字まで入力できます。
- 入力確認画面が表示されたら、入力内容をご確認のうえ[再入力する]または[修了証を発行する]ボタンをクリックしてください。
- [修了証を発行する]ボタンをクリックすると、下図のような修了証が表示されます。ブラウザの印刷機能を使って、印刷したり、PDFファイルに保存してください。
- 別のコースを受講する場合は、修了証の画面を閉じ、当サイトのTOPページから開始してください。